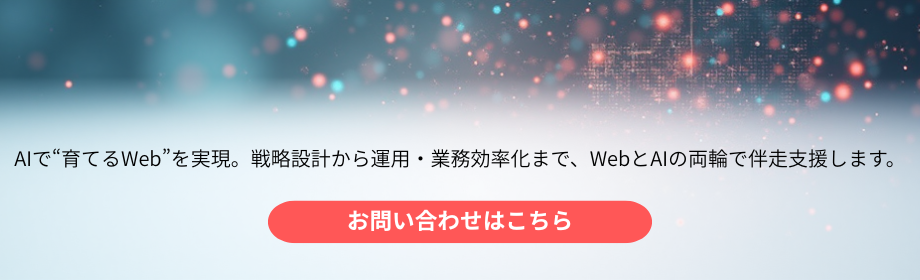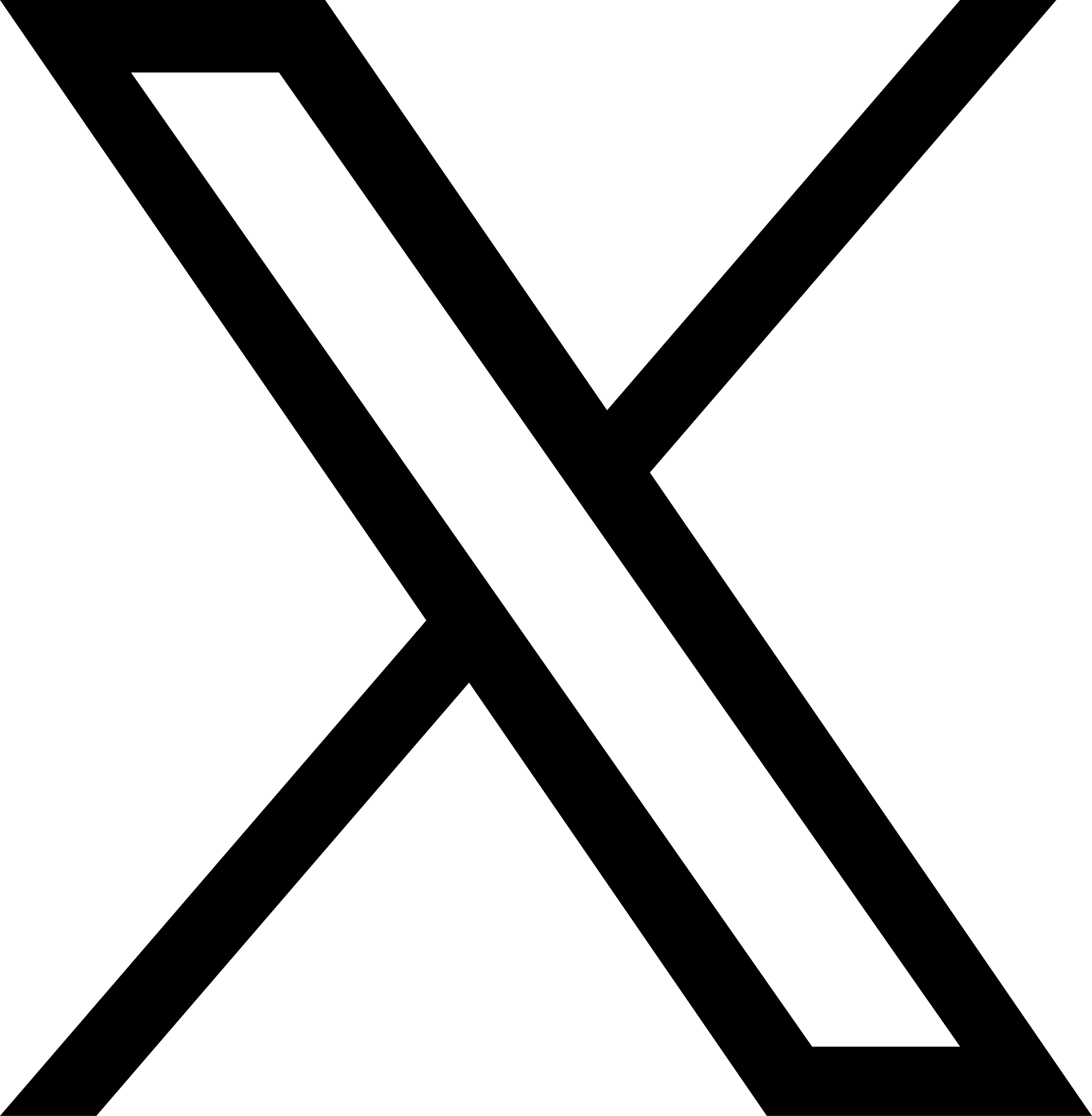Googleに評価されるコンテンツの書き方
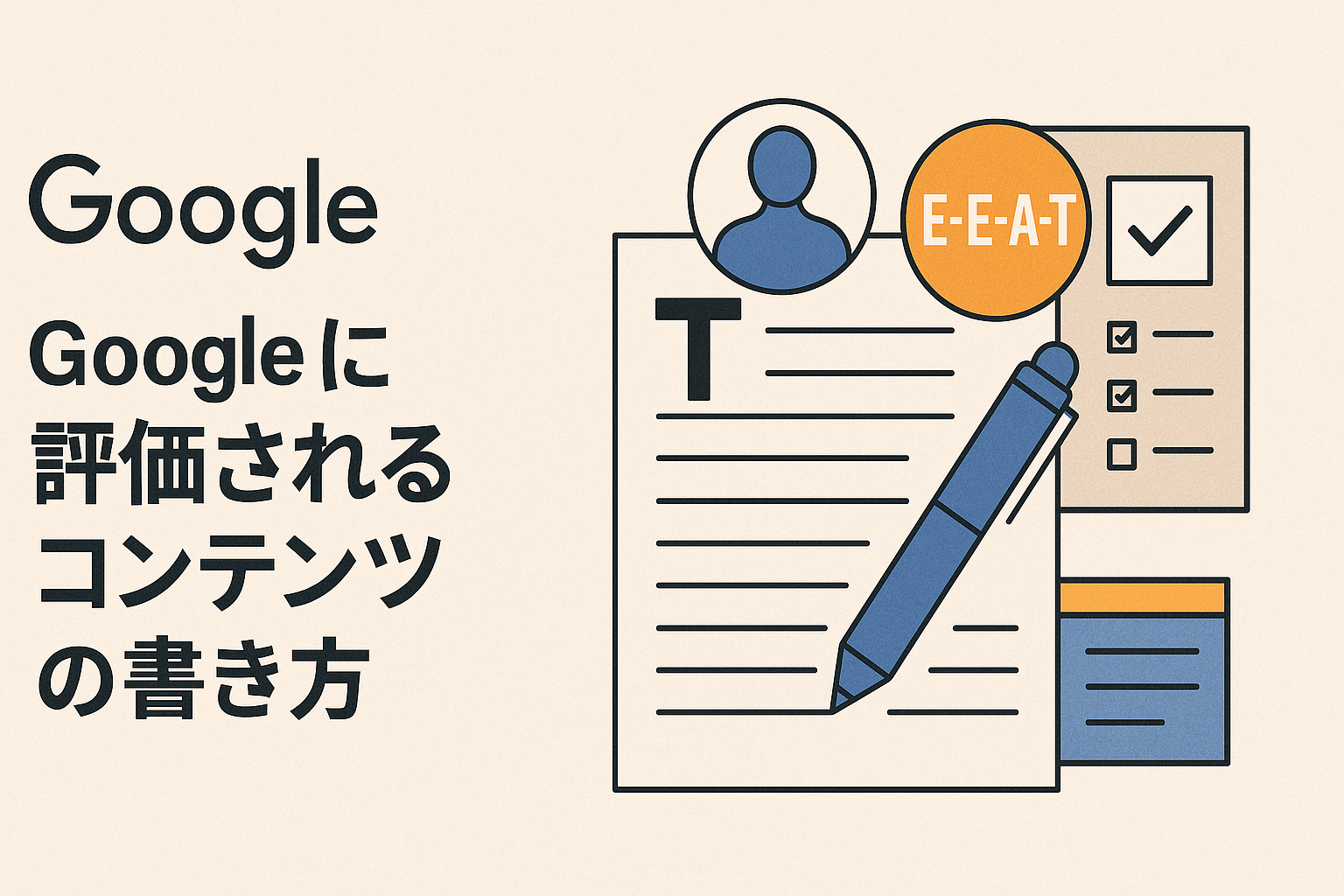
「Google に評価されるコンテンツ(=SEO上で上位を取りやすいコンテンツ)」を書くための実践的ガイドラインをまとめてみました。
後半にはチェックリスト形式でもまとめますので、記事制作時の “落とし穴防止” にも使えます。
まず押さえておきたい前提:Google評価の「軸」
Google(および検索品質評価者観点)でコンテンツが「良い」「高品質」と見なされるには、主に以下のような基準や考え方があります。
Needs Met(ニーズ適合性)
ユーザーの検索意図を満たしており、「このページだけで他のページを探す必要がない」と感じられるか。
Page Quality(ページ品質)
情報の正確性・信頼性・独自性など。重複コンテンツや表面的な内容では評価されづらい。
E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)
最近は “Experience(経験)” が加わり、記事執筆者の一次体験が重視されるようになってきている。
技術的要素・UX
ページの表示速度、モバイル対応、構造化データ、内部リンク、SSL化なども無視できない要素。
これらを総合的に満たすコンテンツが、Google から「良質」と見なされやすいと言われています。
評価されやすいコンテンツを書くための実践ポイント
以下は、実際の執筆段階で意識すべき具体的なポイント群です。
1. “誰が / どのように / なぜ” をクリアにする
Google の公式ドキュメントでも、コンテンツを評価する際に「誰が書いたか」「どのように作ったか」「なぜこの情報を出すのか」の点を明らかにすることが推奨されています。
- 著者プロフィール(肩書、経歴、専門分野)を明示する
- 必要に応じて監修者や参考文献を明示
- 記事の作成プロセス・根拠の明示(例:実データ、体験、調査)
- なぜこのテーマを取り上げたか、読者に対する意図を冒頭近くで示す
これにより E-E-A-T(特に “専門性 / 信頼性”)を補強できます。
2. 検索意図を深く読む(=キーワード設計+意図構造化)
ただ単にキーワードを詰め込むだけでは不十分です。以下を意識しましょう。
- キーワードリサーチ:検索ボリューム・競合記事、関連語(共起語、類義語)を調べる
- 検索意図(ユーザーが “何を求めて検索したか”)を分類
- 情報収集型(「〜とは」「〜やり方」など)
- 比較型(「A vs B」「おすすめ」など)
- 行動誘導型(「購入」「申込」など)
- 見出し構成を、ユーザーの疑問や関心を順序よく解決できる流れにする(序論 → 展開 → まとめ)
こうすることで、コンテンツが “Needs Met(ニーズ適合)” を達成しやすくなります。
3. 独自性と深さを出す
多くの記事は「他サイトの情報をまとめただけ」になりがちですが、Google は重複・浅い内容を低く評価する傾向があります。
差別化を図るために:
- 自身の体験、ケーススタディ、データを入れる
- 具体例・図解・スクリーンショットを用いる
- 比較表、チェックリスト、FAQ といった構造で深掘り
- 最新情報やアップデート情報をフォロー(“鮮度”を担保)
4. 見出し・構造化・マークアップを工夫する
コンテンツの読みやすさ・理解しやすさは、検索評価にも間接的に影響します。
- 適切な階層構造(H2 → H3 → H4 …)
- 各見出しにキーワードや関連語を含める(過剰は禁物)
- 段落は短めに、箇条書き・表組みを活用
- 重要文に強調(太字など)
- 内部リンク/外部リンク適切に配置
- 構造化データ(Schema.org 等で FAQ、レビュー、記事などをマークアップ)
5. 技術的要件・UX改善
コンテンツそのもの以外の要素が足を引っ張ることも多いです。
- 表示速度最適化(画像圧縮、遅延読み込み、キャッシュ利用など)
- モバイルファースト対応(モバイルで快適な読書体験を)
- SSL化(HTTPS) は必須(信頼性向上)
- パンくずリスト / サイトナビ / 関連記事リンク などの導線設計
- 重複コンテンツ排除 / canonical タグ を適切に使う
- 画像の ALT 属性 / ファイル名 / キャプション 設定
6. 更新と改善を前提とする
Google は「鮮度」も判断材料にする場合があります(特に情報性の高いテーマやYMYLジャンル)
- ユーザーコメント/フィードバックを活かして改善
- 定期的な見直し・追記
- 古くなったデータやリンク切れ対応
- 検索アナリティクスで流入キーワードを確認し、追記・修正
チェックリスト:コンテンツ公開前に確認すべき項目
以下のチェックリストを公開前に確認することで、Google に評価されやすい基準を網羅できます。
| チェック項目 | 解説 |
|---|---|
| 著者情報・プロフィールが明示されているか | 名前、肩書、専門分野、略歴など |
| 目的・意図が冒頭で明示されているか | 「なぜこのテーマを書くか」を書く |
| キーワード設計は適切か | 主キーワード・関連語のバランス・過剰詰め込みはないか |
| 見出し構成は論理的か | 読者の疑問を順序よく解消できるか |
| 独自性が出ているか | 単なるまとめ記事ではなく、体験・事例・図解・データを入れているか |
| 内部リンク/外部リンクが適切か | 関連性の低いリンクがないか、信頼できるサイトを参照しているか |
| 技術的要件はクリアか | 表示速度、モバイル対応、SSL、重複排除 など |
| 構造化データ(スキーマ)を使っているか | FAQ、レビュー、記事スニペット対応など |
| 画像の最適化はされているか | ALT 属性、圧縮、キャプション、適切なサイズなど |
| 公開日・更新日の表示(正確性) | 情報が古すぎないか、日付を改ざんしていないか |
| 更新計画・改善体制があるか | 定期的に見直す仕組みがあるか |
上記項目をチェックしてからの記事公開をしてみませんか。