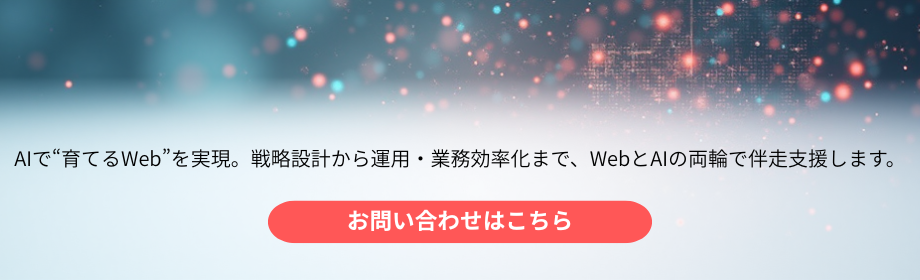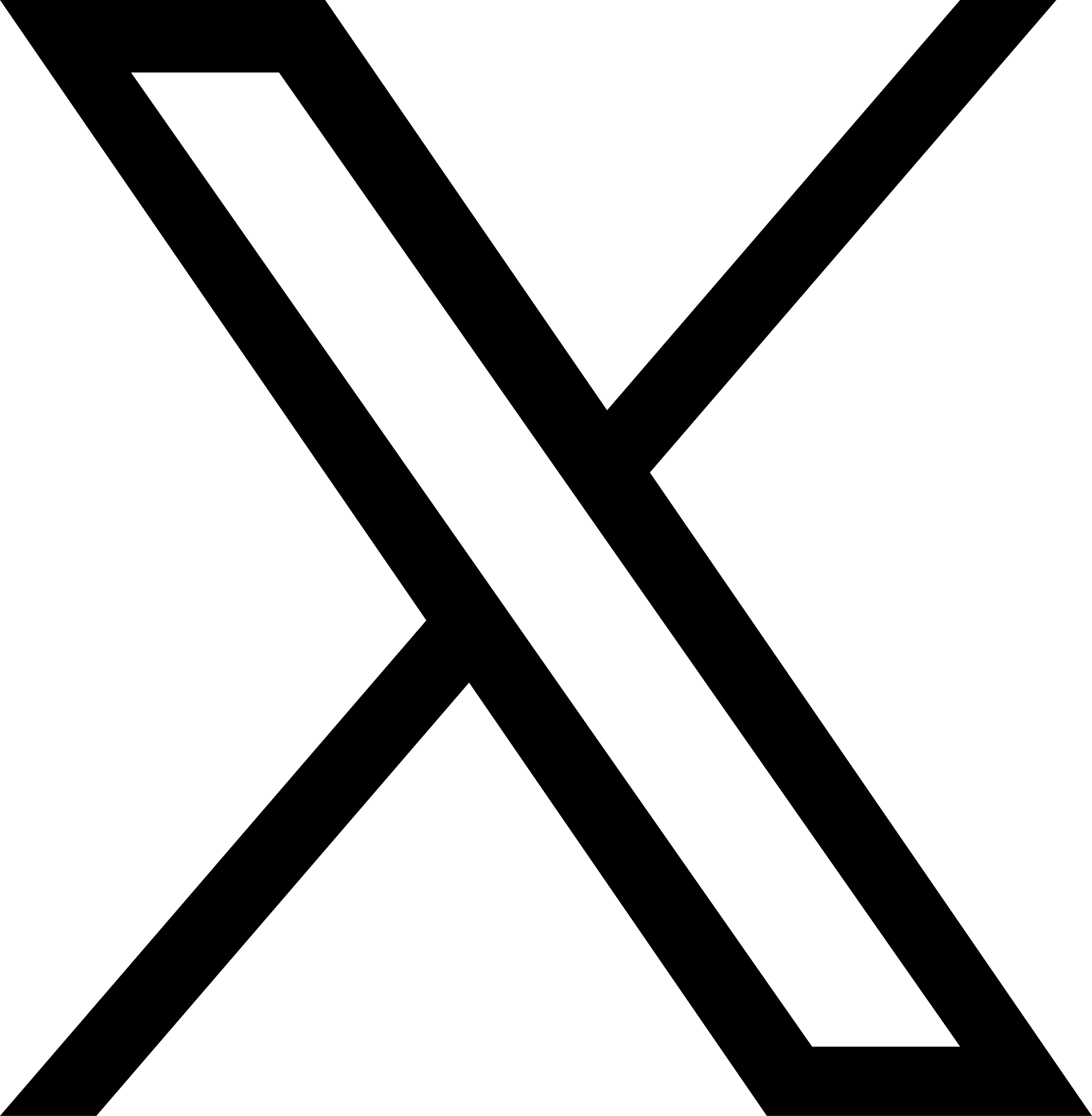ChatGPT(チャット系AI)だけでできる競合サイト分析:手法・プロンプト例・注意点
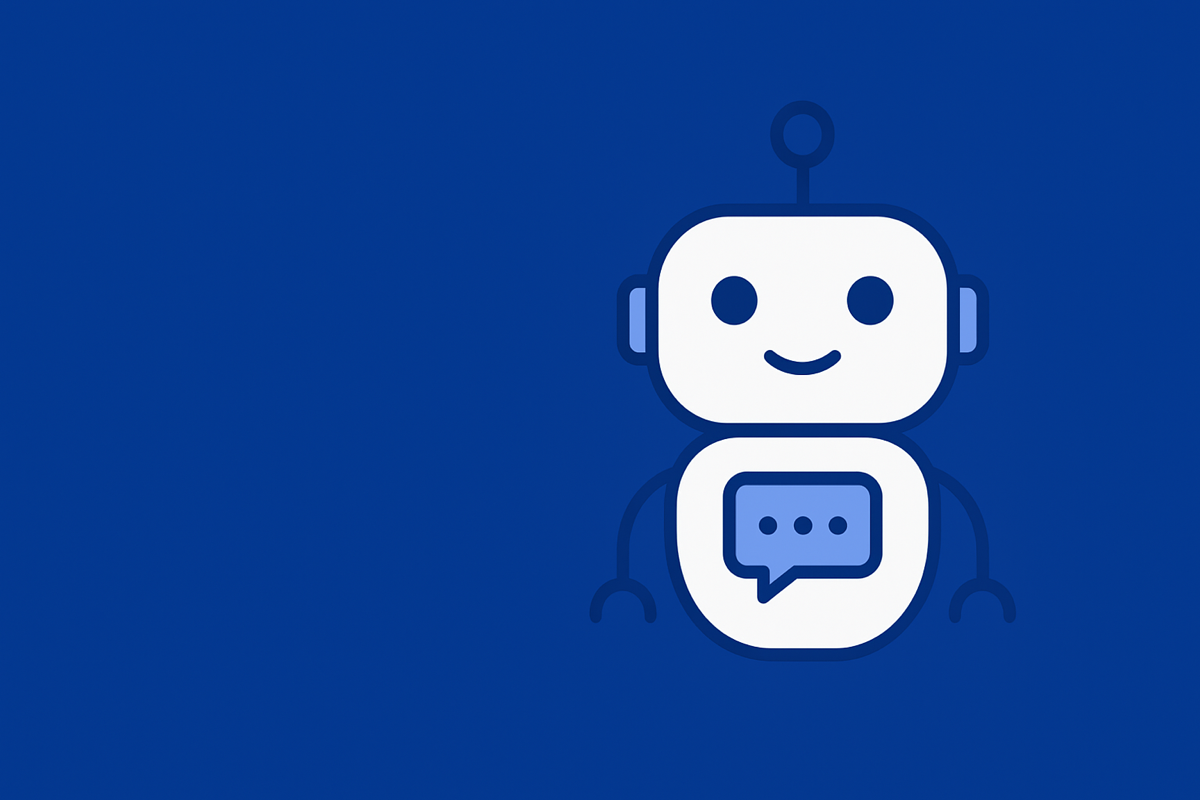
競合サイト分析は、SEO戦略やコンテンツ企画をする上で欠かせない工程です。通常は Ahrefs、SEMrush、SimilarWeb など多くの外部ツールを併用することが一般的ですが、「これらのツールをまだ使えない」「アクセシビリティを重視したい」「コストを抑えたい」という方も多いでしょう。
実は、ChatGPT や他のチャット型 AI に適切なプロンプト(問い)を設計すれば、外部ツールなしでもある程度の競合サイト分析が可能です。本記事では、チャット型 AI の力を最大限引き出す具体的な手順、プロンプト設計、注意点、実践例を交えて解説します。
1. なぜチャット型 AI で競合分析できるか
- ChatGPT(等)は事前学習済みモデルであり、多くの Web 情報や SEO 理論、サイト構造パターンなどを含む知識を持っています。これにより、「ある構造」「見出し構成」「典型的なコンテンツパターン」などを予測・要約する力があります。
- また、複数 URL やドメイン情報を与えて比較を促せば、差異点・共通点・仮説を出してくれることも可能です。
- 最新情報については限界がありますが、公開済みサイト構造やコンテンツ傾向の理解には十分使えます。
ただし、モデルはあくまで「言語モデル」であり、実際のトラフィック数、検索順位、被リンク数などをライブに取得することはできません。これら数値データを扱いたい場合は、最終的に外部ツールと併用する必要があります。
2. 分析対象と範囲の設計
チャット AI に分析を指示する前に、対象範囲と分析軸を明確に設計しておきます。これがないと、AIへの問いが曖昧になり出力精度が落ちます。
チェックすべき設計要素
- 分析対象ドメイン(例:競合 A, B, C、あるいは自サイト+競合)
- 分析軸(例:構造/見出し/コンテンツテーマ/キーワード視点/内部リンク/UI/CTA/レビュー比較など)
- 出力フォーマット(表形式、比較リスト、強み/弱み/改善案など)
- 比較対象の範囲(トップページだけ、カテゴリページも含める、ブログ記事群を対象とする等)
たとえば、次のような前提を ChatGPT に伝えると良いです:
「競合 A と競合 B のトップページ+主要カテゴリページを対象に、見出し構造・導線・主なテーマ軸・強みと弱みを比較してほしい」
この設計をプロンプト冒頭で明記すると、AI が目的に合ったアウトプットを出しやすくなります。
3. 構造・サイト概要の把握
まず、対象競合サイトの「表面的構造」を把握するフェーズ。チャット AI に以下のようにプロンプトを出すと効果的です。
URL: https://example-competitor.com
このサイト(トップページおよび主要カテゴリページ)を見た上で、
- セクション構成(主要なセクション/カテゴリ)
- 見出し階層構造(H2, H3 など)
- サイト構造上目立つ特徴(例:FAQ セクション、統計データ、事例掲載など)
を整理して提示してください。
4. コンテンツ・テーマ分析とギャップ抽出
構造を把握したら、次は「どのテーマ/切り口でコンテンツを展開しているか」を見ていきます。AI にコンテンツ分析を頼む際は、見出し+本文抜粋(または要約)を渡すのが有効です。
以下は競合サイト A の「カテゴリ X」に属する記事 5 件の見出し+要約(または冒頭文)です。
(見出しと要約を列挙)
この中から主なテーマ群を抽出し、それぞれキーワード構造(共起語、関連語)を提示してください。
さらに、これらテーマを自サイトと比較した際の「ギャップになりうる切り口案」を 3 つ提案してください。
AI はテーマ分類、キーワード構造提示、ギャップ案提案まで行ってくれます。特に「競合が触れてない切り口」「キーワードの強み弱み」などを引き出すことが目的です。
この手法では、レビュー記事・ブログ記事・FAQページなどから見出し+抜粋をなるべく多めに渡すと分析精度が上がります。
5. キーワード・SEO 視点からの比較(プロンプト式)
チャット型 AI 単体で「実際の検索順位データ」を取得できるわけではありませんが、「競合が使っていそうな狙いキーワード」「タイトル/メタディスクリプションで意識していそうなキーワード」「最適化傾向」などを推理・仮説化してもらうことは可能です。
競合サイト A のトップページタイトル、メタディスクリプション、主要見出しを示します:
(タイトル、description、見出しを列挙)
この情報から、「この競合が狙っているキーワード(主キーワード/副キーワード)」「SEO 視点で意識していそうな最適化傾向(例:ロングテール/疑問形/地域名併記など)」を 3 つずつ仮説化してください。
さらに、自サイトがその仮説キーワードで抜けている可能性のある切り口案を 2 つ出してください。
また、複数競合を対象にすれば、どのキーワードが共通して狙われやすいか、差別化しやすい切り口はどこか、などを比較できます。
6. UI/UX・導線観察・改善仮説出し
競合サイトの UI/UX(導線設計、CTA ボタン配置、ファーストビュー構成など)は、訪問者を離脱させないために強く設計されているケースがあります。これもチャット AI に観察を仮定的にさせて、改善仮説を引き出させます。
競合サイト A のトップページおよび主要カテゴリページのファーストビュー・ナビゲーション・CTA 要素を見た仮定で、
- 強みと弱み(ユーザー導線観点)
- 直帰率を下げる可能性のある改善仮説を 2 つ
- 自サイトに取り入れられそうな導線アイデア
を整理して提示してください。
ここでは実際にサイトを見せるわけではないため、AI に「仮定観察」を促すように文脈を整えておくのがポイントです。
7. 顧客視点(レビュー・口コミ分析)
競合の商品やサービスに対する顧客の声、レビュー、口コミ、Q&A コメントなどを収集して、AI に分析させることで「ユーザーが抱えている不満・期待・要望」を見つけられます。
以下は競合商品に対する口コミ・レビューコメントの抜粋 10 件です:
(レビュー例を並べる)
このレビューから、
- ポジティブ要因
- ネガティブ要因
- 頻出語(共起語)
- 顧客が本当に求めている改善点・要望
を整理してください。
その上で、自サイトが取るべき対応施策案を 2 つ提案してください。
AI はレビュー分析・顧客議論抽出まで対応できます。ただし、レビュー数が少なすぎると有意性が取れないため、できる限り多数のレビューを拾っておき、代表的なものを抜粋して渡すとよいでしょう。
8. 分析まとめと改善案整理
各分析軸が出そろったら、AI に「総合まとめ+改善優先順位付け」を求めて、最終的な戦略案を出してもらいます。
これまで構造比較、テーマ分析、キーワード仮説、UI/UX 仮説、レビュー分析を行いました。
これらの出力から、
- 競合と比較しての自サイトの強み・弱み
- 優先的に取り組むべき改善テーマ(上位 3 つ)
- 各改善テーマごとに具体的アクション案
を整理して提示してください。
この段階で、AI に整理されたマトリクス形式(強み/弱み/機会/脅威 = SWOT 形式)での提示を求めるのも効果的です。
9. ChatGPTでの実践プロンプト集(テンプレートまとめ)
以下は、チャット型 AI に投げかけやすいプロンプトのテンプレート集です。用途別に整理しました。
| 目的 | プロンプトテンプレート |
|---|---|
| 構造分析 | 「URL: ○○ を見た上で、主なセクション/カテゴリ構成および見出し構造を整理してください」 |
| 複数競合比較 | 「A・B・Cのサイト構造を比較し、共通点・差異・注目すべき設計を 3 つずつ挙げてください」 |
| テーマ抽出 | 「記事見出し+要約を渡すので、主なテーマ群とキーワード構造を抽出してください」 |
| ギャップ提案 | 「競合テーマと自サイトテーマを比較して、切り口ギャップ案を 3 つ出してください」 |
| キーワード仮説 | 「タイトル・見出し情報から狙いキーワード仮説を出し、差別化案を提示してください」 |
| UI/UX 評価 | 「仮定でサイトを見たうえで、導線強化案・改善仮説を 2~3 出してください」 |
| レビュー分析 | 「レビューコメント抜粋を渡すので、ポジティブ/ネガティブ要因・要望抽出をしてください」 |
| 総合戦略案 | 「各分析出力から、自サイト強み・弱みと改善テーマ+アクション案を整理してください」 |
これらを適宜連続して投げていくことで、ChatGPT 主導で「競合サイト分析 → 戦略立案までの流れ」を実施できます。
10. 限界と注意点・補強手段
限界・リスク
- 数値データをリアルタイムに取得できない
トラフィック数、被リンク数、検索順位などは外部ツールに頼らざるを得ません。 - モデルの知識鮮度の制約
ChatGPT は学習済み知識を基に応答するため、最新のキャンペーンや UI 変更を把握できていないことがあります。 - 仮説的・予測的な出力になる
AI の分析は「可能性が高そうな仮説」であり、必ずしも正確とは限りません。人間による検証・補正が必要です。 - プロンプト設計の精度依存
プロンプトが曖昧・不十分だと、出力もぶれやすく意味の薄いものになるリスクがあります。
補強手段
- 必要に応じて、外部ツール(Google Search Console, Google Analytics, Ahrefs 等)のデータを後から統合して裏付けする
- AI 出力に対して、自身で少量サンプル検証(実際に競合のタイトルや見出しを目視確認)を行う
- 分析作業を定期的に更新(半年〜1年ごと)して、モデルの古さによるズレを補正
- 異なるプロンプト・角度で再質問し、結果のブレ幅を確認して信頼度を判断
11. まとめと次ステップ
チャット型 AI(ChatGPT 等)だけを使って競合サイト分析を行う方法は、コストや導入ハードルを抑えつつ、構造・テーマ・UI・レビュー視点から豊かな仮説を立てられる実用的なアプローチです。ただし、「ツールで測定された定量データ」と比べると精度は劣るため、あくまで仮説マップ生成+仮説検証の入り口として使うのがベストです。
次のステップとしては:
- この記事で紹介したプロンプトを実際に ChatGPT に投げてみる
- 出力内容を自サイト・競合サイトで改めて目視チェック・検証
- 必要に応じて外部ツールやアクセス解析データを統合
- 分析プロセスをテンプレート化し、次回以降すぐ使えるようにする
ChatGPTなどでもこれだけのことが出来るので、試して見る価値はあるのではないでしょうか。
ぜひ、お試しください。
レポート作成や調査などの代行を依頼したい場合は、AIミライデザイナーにご相談ください。