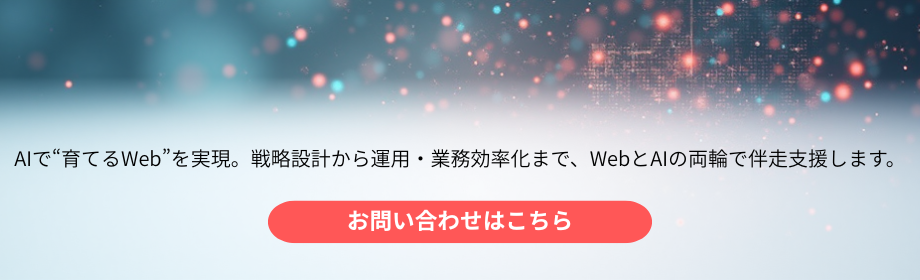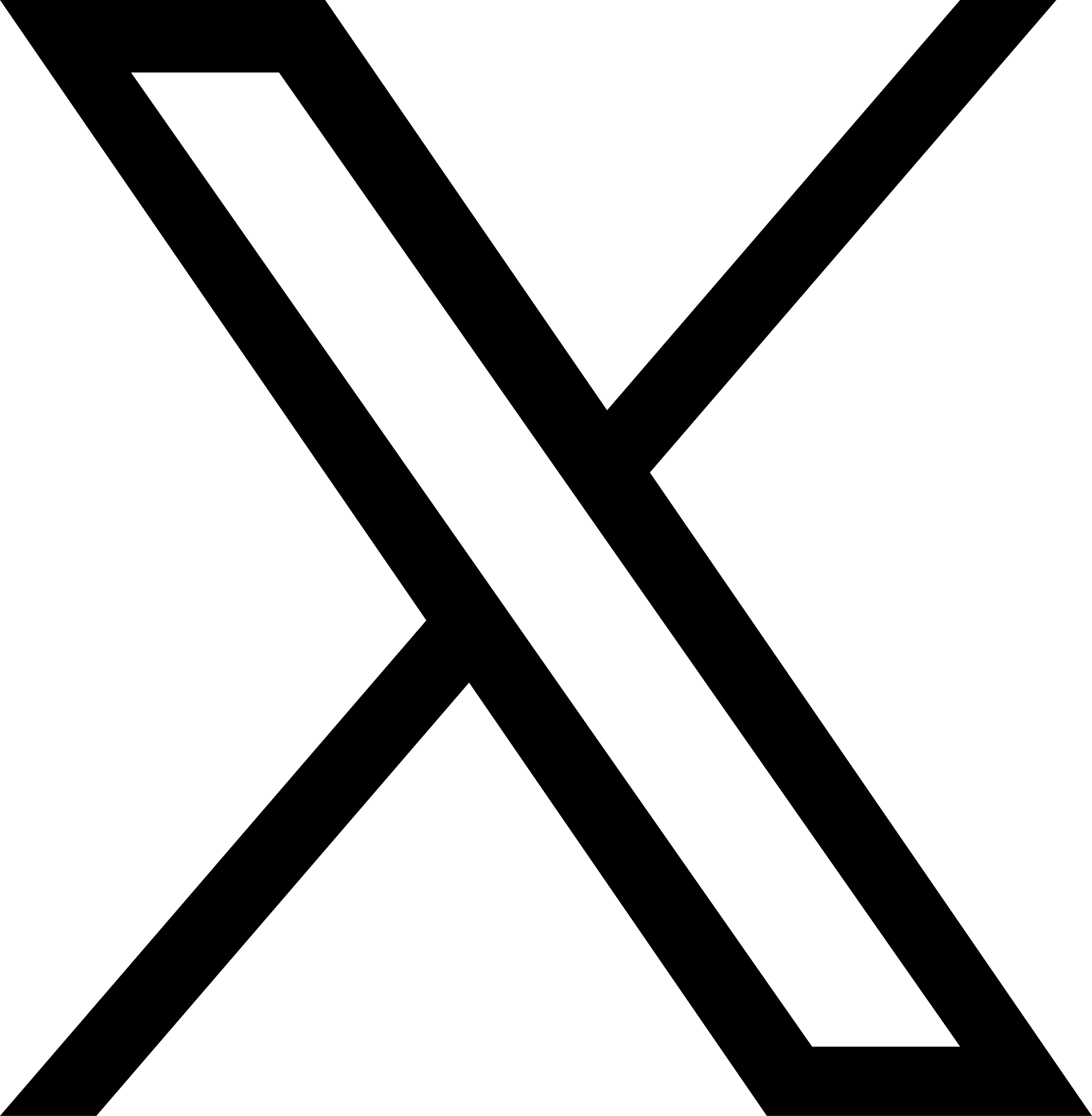SEOを意識したページ構成の作り方
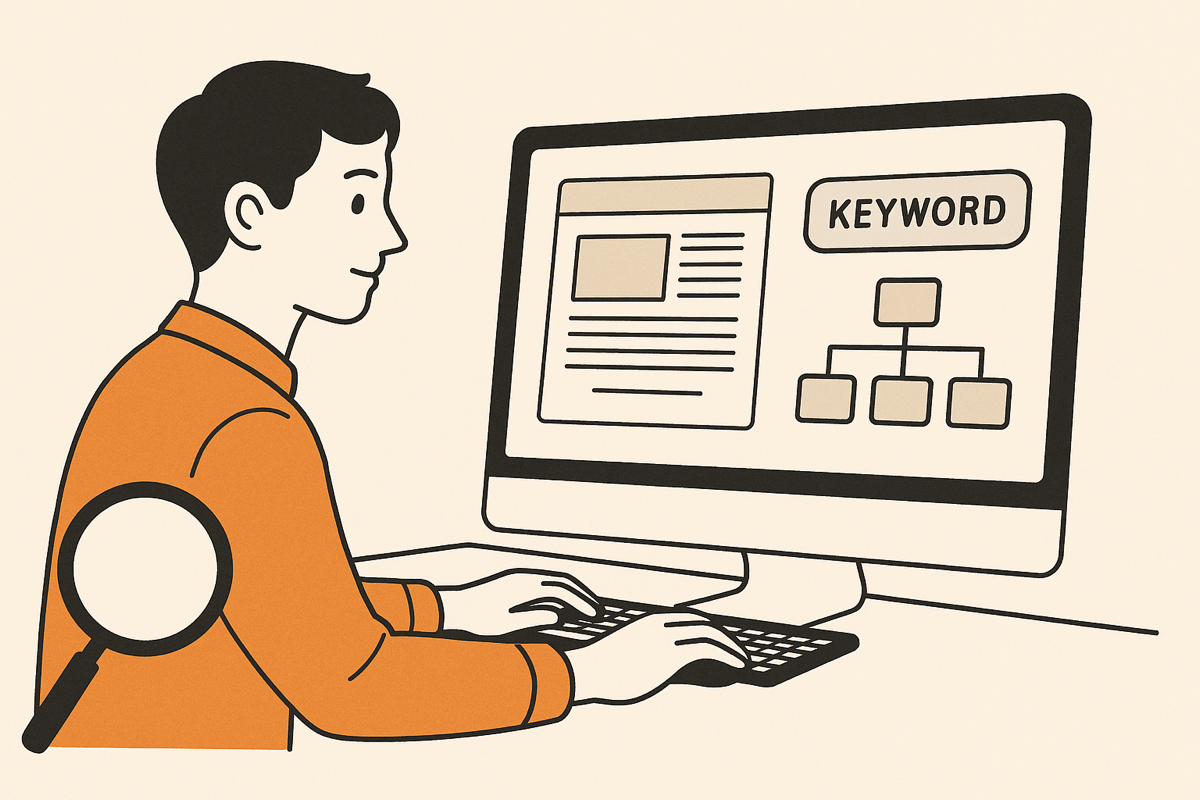
以下では「SEOを意識した ページ構成(=ウェブページ/サイト構造) の作り方」について、理論と実践の両面から丁寧に解説します。
この記事を読めば、自サイトの構造をSEO観点で最適化するためのロードマップが得られます。
1. SEOにおけるページ構成・サイト構造の意義
まず、なぜ「構成(構造)」がSEOで重要なのかを確認しておきましょう。
1.1 検索エンジンがクロール・理解しやすくなる
適切なページ構造・内部リンクがあれば、Googleなどのクローラーがサイトを巡回しやすくなり、ページの発見・インデックス化の精度が向上します。
1.2 ユーザー体験(UX)の改善
利用者が目的の情報にたどり着きやすければ、離脱率の低下・滞在時間の増加などが期待でき、それが間接的にSEOに好影響を及ぼします。
1.3 内部リンクの最適配置・評価伝播
階層構造と内部リンクで、サイト内の重要ページ(コアページ)にリンク価値を集中させる設計が可能になります。逆にリンクが散漫だと SEO 効果が希薄になります。
1.4 キーワード構造の整理と重複回避
ページ構成にキーワードテーマを反映させ、似た内容のページがばらばらに配置されて重複コンテンツやカニバリ(自サイト同士の競合)を避けられます。
2. ページ構成を設計するステップ(ロードマップ)
以下の段階を順番に設計していくことをおすすめします。
| ステップ | やること | ポイント/注意点 |
|---|---|---|
| ① 全体マップ(サイト構造案)を可視化 | まずはサイトの構成を図で描いてみる | トップページ → カテゴリ → サブカテゴリ → 個別ページという樹形構造を意識する |
| ② キーワード整理とテーマ設計 | サジェスト語や類似語を使って各ページ/カテゴリのテーマを決定 | 似たテーマ同士を同じカテゴリ内にまとめ、重複を避ける |
| ③ URL設計・ディレクトリ設計 | URL を “カテゴリ/サブカテゴリ/スラッグ” の階層にそろえる | 人が見て意味が分かる「クリーン URL(意味を含む URL)」とすべき |
| ④ ナビゲーション / メニュー設計 | メニュー(グローバルナビ、サイドバー等)を設計 | 主要なカテゴリを明示、階層を深くし過ぎないようにする |
| ⑤ 内部リンク設計(文脈リンク含む) | 各ページ内から関連ページへリンクを張る | アンカーテキストに適切なキーワードを含め、文脈に即したリンクを張る |
| ⑥ サイトマップ・パンくず等補助構造 | XMLサイトマップ、HTMLサイトマップ、パンくずを整備 | 検索エンジン・ユーザー双方への案内を強化 |
| ⑦ 継続的な最適化・監査 | 古いページの統合・リンク切れチェック・サイト構造の見直し | サイトが大きくなっても秩序を保つようメンテナンスを行う |
以下、各要素をより詳細に見ていきます。
3. 各設計要素の具体ポイント
3.1 階層(リンク階層・浅さ)の最適化
- 浅めの構造(=「フラット構造」) が理想。トップページから 3~4クリック以内で各ページに到達できるようにするべきです。
- 深過ぎる構造(多数のサブサブ階層)は、クローラーが辿りにくく、リンク価値が薄まりやすいというデメリットがあります。
- ただし、小規模サイトなら、カテゴリ構造を簡素に保っても問題ないケースがあります。
3.2 URL 構造設計
- URL は 説明的でわかりやすい構造 を採るべき:例)/カテゴリ名/サブカテゴリ/ページ名 という形式。
- スラッグ(URL末尾部分)はできるだけキーワードを反映させ、意味を持たせる。不要語(a, the, of など)は省く。
- 単語間はハイフン(-)で区切るのが推奨手法(アンダースコア _ は避ける)
- URL は一貫性を持たせ、あとで構造変更しやすいよう配慮する。
3.3 ナビゲーション(グローバルメニュー等)
- トップナビゲーション(メインメニュー)には、重要カテゴリを入れる
- メニュー数が多過ぎると煩雑になるので、主なカテゴリを絞る
- パンくずリスト(breadcrumb)を導入し、ユーザーが今どの階層・位置かを把握できるようにする
- サイドメニューやフッターメニューなど補助的なリンクも併用して構造を補強
3.4 内部リンク設計(文脈リンク・階層リンク)
- 見出しや本文中から、関連する記事やカテゴリページへリンクを張る
- アンカーテキストは適切なキーワードを含めて自然にする
- ただし、リンクを張りすぎると逆効果(スパムリンク扱いなど)になる可能性もあるため適度に制御
- 重要ページ(コアページ)は意図的に多く内部リンクを張られやすくする
- 孤立ページ(内部リンクがほとんどないページ、Orphan ページ)を作らないよう注意する
3.5 サイトマップ・補助構造
- XML サイトマップ:検索エンジン向け。インデックス対象を明示的に伝える。更新時に再送信
- HTML サイトマップ:ユーザー向け/補助的なナビゲーション
- パンくず(Breadcrumb):ユーザーと検索エンジン双方に構造提示
- 構造化データ(Schema.org 等):よりリッチな検索結果やパンくず制御に使える
- URLや階層が変わる場合、301 リダイレクトや正しい canonical 指定を忘れない
3.6 維持管理・最適化サイクル
- 定期的に SEO 監査を行い、リンク切れ、重複ページ、構造の偏りをチェック
- コンテンツを統合・更新・削除し、構造をリファイン
- サイトが成長するほど、カテゴリや階層の見直しを検討
- 追加するページが構造に整然と収まるようルールを維持
4. ページレベルでの構成設計(個別ページ)
ここまでがサイト全体としての構造設計ですが、個々のページを作るときにも構成(章立て・見出し構造など)を SEO 観点で意識する必要があります。
以下は「記事ページ/コンテンツページ」を例にした構成ポイントです。
4.1 記事構成の基本ステップ
- 狙うキーワード/検索意図の明確化
- 関連キーワード・共起語の洗い出し
- 見出し構成(H2/H3)を先に設計
- 各見出しに含める内容(要点・結論)を先に整理
- 書き出し(リード)・まとめ・FAQ など補強要素を設ける
この流れは一般的にもよく使われており、SEOに強い記事構成として「7ステップ」などに整理されています。
4.2 見出し構造のルール
- H1:ページのタイトル(狙いキーワードを含める)
- H2:主要トピック(上位テーマ)
- H3:H2の細分テーマ
- 見出しは論理的な階層構造を保つ
- キーワードを詰め込み過ぎない自然な表現
- 見出しだけで内容の流れがわかるように設計すると読者満足度も上がる
4.3 本文中の注意点
- 各セクション冒頭に結論を示し、それを説明・補強する構成
- 適切に内部リンクを散りばめ、読者を他ページへ誘導
- 段落の長さを適切に保つ(長すぎない)
- 画像・表・引用・リストなどで視覚的アクセントを入れる
- メタ要素(title, meta description)・alt 属性等もキーワード設定を意識
5. 構成例:美容クリニックサイトを想定
たとえば「横浜 美容クリニック」というテーマでサイトを作るなら、下記のような構成案が考えられます。
トップページ
├ 処置別カテゴリ(例:しみ・肝斑、ボトックス、ヒアルロン酸、レーザー)
│ ├ しみ・肝斑ページ
│ │ ├ 原因と対策
│ │ ├ 治療法の比較(レーザー/内服/外用)
│ │ ├ 料金・症例
│ │ ├ よくある質問
│ ├ ボトックスページ
│ └ …
├ クリニック紹介(医師紹介・院内紹介)
├ よくある質問集
├ お知らせ・コラム
└ アクセス・予約ページ
- 各カテゴリページは「美容テーマの柱(pillar)」に
- コラム・ブログ記事は、カテゴリに属するサブトピックごとに分類・内部リンク
- “よくある質問” や “症例紹介” は補助的コンテンツとして内部リンクを回す
このように、テーマ別に整理されたカテゴリ構成があると、SEO的にも強くなりやすいです。
6. よくあるミスと注意点チェックリスト
以下は構成設計段階でよくあるミスと、それを避けるためのチェックリストです。
| ミス・課題 | 回避方法 |
|---|---|
| 階層が深すぎてクリック数が多くなる | 構造を見直して浅くまとめる |
| URL が意味を持たないランダムなもの | スラッグや階層設計を見直す |
| 内部リンクが散漫/関連性が低い | 文脈に即したリンク設計、孤立ページなしに |
| メニューにリンク数が多すぎて煩雑 | 主要カテゴリを絞り込む |
| 古いページが残り続けて構造が乱れる | 定期監査で統合・削除・リダイレクトを実施 |
| 重複コンテンツ/カニバリ現象 | テーマ分類とキーワード整理を徹底 |
上記チェックリストなどをもとに、サイト改善を進めていきましょう。
あまりにも変更範囲が多ければ、リニューアルを検討するのも手です。リニューアルをもって、土台を固めて再スタートを切るのも選択肢にしていきましょう。
スピーディーなサイトリニューアルはAIミライデザイナーにお問い合わせください!